私のような自営業も大変ですが、会社勤めをしていても、リストラがあったり再就職しようにも難関だったり、大変ですね。そんな渦中の方にはどうぞ頑張ってくださいとエールをお送りします。
実は先日、リストラにあっていた私の友人が、再就職に挑戦しました。
そしてそこで小論文の試験があって「苦労しちゃったよ」ということを聞きました。
そんなことからこの記事では「型を使って、小論文をなるべく簡単に書く方法」についてまとめてみました。
なおこの記事は、別記事で書きました『小論文のコツは書き出しの「問題提起」!これができれば半分完成』とペアのつもりで書きました。もしそちらをご覧になってなければ、併せてお読みいただければと思います。

別記事では、小論文の作り方の中で
- 与えられたテーマ(課題)から切り口を考え、問題提起文を作るまで
- 問題提起で注意したい3つのポイント
などを書きました。
こちらの記事では、問題提起ができたあと、どう展開して結論まで持っていくかをお伝えします。また、実際の作例もご紹介します。
結論までの展開の方法はいろいろありますが、試験という限られた時間で最も簡単にできるのは、型(テンプレート)にあてはめる方法です。
型もいろいろありますが、この記事では「だろうかたしなよ型」とか「反論容認型」と言われるものをご紹介します。
小論文は型にあてはめると簡単!ポイントは「だろうか たしなよ」
この型は以前、NHKの番組でやっていたもので私のオリジナルではありません。ですが番組で言っていた形では少し足りないと思いましたので、私流に少しアレンジしています。
この型の流れは「問題提起」⇒「反対意見への理解」⇒「自分の意見を提示」⇒「理由説明」⇒「結論」という5つのステップになります。
反対意見にいったん理解を示すことから「反論容認型」とも言われています。
まずはその流れを図にしましたので、ご覧ください。

型を使って実際に作ってみましょう!
それではこの型(テンプレート)を使って、実際に小論文を作ってみましょう。
課題の例として、問題提起の記事で取り上げました「社内の人間関係を良くする方法」をそのまま使ってみます。そちらを先にご覧になった方は続きという感覚でお読みください。
社内の人間関係を良くする方法ついて、タイトルを含め800文字であなたの提案を書いてください。
試験としては多分800文字か1,000文字が多いと思うので、ひとまず800字ということにしてみました。
課題に対して書きやすい切り口をみつける
課題が与えられたら、まずそれに対して自分が書きやすい切り口を考えてみます。
いったん数多くアイデアを出す
まず、自分が社内のいろんなシチュエーションで「これで社内の人間関係が良くなるだろう」と思うことをできるだけ多く考えます(可能であれば書き出します)。これはとても大事なことです。
- 挨拶など簡単なことで、社内の人間関係を良くする方法がないか?
- 仕事中に気をつけることで、ないか?
- 昼食や休憩時間にできることで、ないか?
- 仕事が終わった後にできることで、ないか?
などいろいろ考えてみましょう。
ただ、試験ということであれば時間制限があります。自分なりに例えば「5分間」などと決めて、その間頭をフル回転させてください。
書きやすいものを一つ決める
考えた切り口の中で自分が最も書きやすい、もしくは自信を持って書けるものを選びます。
今回は「仕事後に上司と一緒に飲みに行くことが、人間関係を良くする」という話にしてみようかと思います。
「飲ミニケーション」などと言われることもありますが、同時に、業務時間が終わった後も仕事の関係が続くことを嫌い、否定する若い人の話もよく聞きます。賛否両論がありますし、私自身気になっていることなので、取り上げてみました。
1「問題提起」
「上司や先輩との飲みは良いものである」という肯定的なイメージのもと、文末に「〜だろうか」をつけた文を考えます。
今ごろは「就業時間が過ぎれば会社とは無関係」と、仕事が終わった後の食事会や飲み会を否定する若者も多いと聞くが、人間関係の面で、それでほんとにいいのだろうか。
ここまでが問題提起です。
課題によっては肯定的な論調・否定的な論調どちらでもできますが、この課題ですと「こうすれば良い」という肯定的な論調にならざるを得ませんね。
2「反対意見への理解」
文頭に「確かに〜」文末に「〜かもしれない」または「〜とわかる(理解できる)」をつけて、否定的な意見に一度理解を示します。
確かに、プライベートな時間は誰にとっても非常に大事なもので、そんな時まで上司や同僚と一緒にいたくないというのは理解できる。
3「自分の意見を提示」
文頭に「しかし私は〜」をつけて、自分の意見を示します。
しかし、私は上司や先輩との仕事後のおつき合いも、(程度問題はあるが)大事なものだと考える。
4「理由説明」
文頭に「なぜなら〜」文末に「〜だからだ」をつけて、その意見を出した理由を書きます。
なぜなら私は、新入社員だったころ、上司からの仕事後のお誘いを受けることで、なんでも話せるようになり、人間関係がすごく良くなった経験があるからだ。
5「結論」
文頭に「よって私は〜」文末に「〜と考える」をつけ、結論づけます。
よって私は、頻度など注意点はあるが、上司や先輩との仕事後の飲食のつき合いは、社内の人間関係を良くするのに役立つと考える。
そんな感じですね。いかがですか。すんなりはまるでしょう?
これで骨格ができました。
あとはこれに自分の体験談を加えたり、意見を補足します。また、このままでは言葉が硬いですから自分流に柔らかくしていきます。
そうすれば楽に規定の文字数になりますし、よりよく伝わる文章になりますよ。(通常、多少多めに書いて削って文字数を調節する方が楽です)
具体的な主張(提案)としては
- 仕事を離れたところで上司と飲食しながら話す → 本音が話せて人間関係が近くなり、良い影響がある
- ただし、無理な誘いは問題だし、パワハラになる危険もあるので、誘う側も注意が必要
という2つのポイントを中心にしました。
「結論」は「よって私は〜〜と考える」のパターンで入れていますが、課題が「あなたの提案を書いてください。」ですから、最後は「以上のことから〇〇を提案します。」という形で締めくくりました。
ということで、「社内の人間関係を良くする方法の提案」という課題を、私なりに一つの小論文に仕上げてみたものがこちらです。テンプレートの部分は色を変えました。
社内の人間関係を良くする方法について、私の提案
会社での人間関係を良くする方法について、私なりに考えてみました。私が提案したいのは、仕事が終わった後の上司や先輩との食事会・飲み会についてです。
特に若い社員の皆さんに伝えたいと思います。
今、若い人の間ではプライベートを最優先する傾向が強く、上司や先輩と仕事外で食事や飲みをあまりしたがらないと聞きます。でもほんとにそれでいいのでしょうか?
もちろん仕事が終わればその後はプライベートな時間です。そこまで仕事の関係を引きずったり、上司とつき合うのが嫌だという気持ちは理解できます。
しかし私は、上司との仕事後のおつき合いも、程度はありますが大事なものと考えています。
なぜなら私自身、新入社員だったころ、上司と仕事後にお酒を飲むことで打ち解けて話せるようになり、互いの関係がすごく良くなった経験があるからです。
仕事中は仕事に関する話以外はあまりできませんし、心を割ってゆっくり話すなんてこともありません。そういう中で互いの人間性を分かりあうのは難しいものです。
怖いと思っていた上司や先輩でも、そういう席ではうって変わって楽しい一面を見せてくれることもよくあります。お互いの本音も仕事後のそういう場でこそ話しやすいということも多々あります。
もちろん問題もあります。本当に用事があったり内心嫌だったりしても上司や先輩からの誘いとあれば断りにくいでしょう。「オレにつき合えないのか」などとパワハラもどきのことを言う上司もあるかもしれません。
その点は誘う側の上司の方々に十分注意してほしいことです。若い社員さんの立場も考えて、押しつけがましくならないようにしていただきたいです。
よって私は、この時代だからこそ、今一度「飲みニケーション」を見直すことによって、より互いを理解し、より良い関係を目指せると考えます。
以上、社内の人間関係を良くする方法として私の提案です。
これでタイトルを含め797文字です。
文章は「誰に向けたものか」というのも大事なポイントです。
今回は「若い社員さんに向けた文章」として書きましたが、途中ちょっと「上司」に向けた部分もあって、そこはちょっと難しいと感じました。もう少し直せるとも思います。
それではもう一つ作例を作ってみます。
「800文字の小論文」作成例-2〈会社の無駄節減について〉
ある会社の中で、昇進試験として小論文があったと仮定してみました。
当社における無駄の節減について、タイトルを含め800文字以内であなたらしい提案をしてください。
自分が社内を見ていて感じるいろいろな「無駄」があると思います。そこを書けば良いのですが、今回は仮に「会議の無駄」という話にしてみます。社内会議が全て無駄というつもりはないのですが、ここはあえてそれを問題視してみました。
まず1〜5の各パーツですが
1「問題提起」
まだまだ頻繁に社内会議が行われている会社が多いのではないかと思える。本当にここまで要るのだろうか。
2「反対意見への理解」
確かに、会社のいろんな問題点、仕事の進行、すり合わせなどは、集まって会議をしないといけないというのもわかる。
3「自分の意見を提示」
しかし、私はその全てが必ず顔を合わせないといけない会議だとは思わない。
4「理由説明」
なぜなら、今は全社員がメールを使えるし、テレビ電話システムもある。同報メールやテレビ電話会議をもっと利用すれば、会議を開く必要が半減するはずだからだ。
5「結論」
よって私は、メールやテレビ電話システムの工夫・採用によって会議をもっと減らすことができ、それが社員の時間や費用の削減につながり、会社の無駄節減に大きく役に立つと考える。
としました。それらに肉付けをして書いてみた小論文(提案文)の例がこちらです。
これも分かりやすいよう、テンプレートの部分は色を変えました。
当社の無駄節減についての提案
当社の無駄節減ということで私なりにいろいろと考えてみました。今私が最も無駄を感じるのは「あまりにも会議が多いこと」です。今回はこれについて書きます。
現在社内では毎週多くの会議が行われています。私は平均して週に4回はなんらかの会議に出席しています。ですが本当にここまで必要なのでしょうか。
もちろんその全てが無駄だというつもりはありません。
確かに、仕事の進行やチェック・すり合わせ、あるいは社内外の問題について話し合うなど、担当者が顔を揃えて会議をする必要性も認識しております。
しかしながら、私は、その全てが必ずしも顔を合わせないといけない会議だとは思いません。
なぜなら今は全社員がパソコンやスマホを持ち、メールもオンラインチャットもできるからです。
まずはこれまでの会議の内容を今一度精査して、会議という形でなくても済むものがあるのではないか、考えた方がいいと思います。
個々がそれらのチェックを怠らないという前提ではありますが、メールやオンラインチャットで事足りることも結構あります。
また今はスカイプやZOOMなどのオンライン会議システムが安定して使えます。
そういうシステムを全社員が自由に使えるようになることで、必ずしも会議室に集まらなくても、各自が今いる場所で会議ができます。
まだ使えない社員がいることは承知しておりますが、今後、勉強会や個々の意識改革で変わってくるはずです。
よって私は、会議の内容の見直しと、オンラインチャットやスカイプ等を使うことによって、現行の会議は大幅に減らすことが可能だと考えます。
全ての会議が無駄とは申しませんが、これらの導入により、社員の時間や費用の削減にもつながりますし、社員がより動けるようになり、仕事にゆとりを持てるようになります。
以上、会議内容の見直しと、オンラインチャットやオンライン会議のさらなる導入を提案します。
タイトルを入れて792文字です。
是非を逆に展開することもできます。
「今の時代、オンラインで会議をすることが増えてきているが、それでも直接会って会議をした方が良い」という結論です。
- リモートで会議をするのは便利だが、本当にそれで細かいことまで伝わるのだろうか
- 直接会って同じ空間で話をした方が、互いの気持ちが理解しやすく、質問もしやすい
- 回数を見直す、時間を区切るなど、工夫をすることで、以前より効率的な会議にすることは可能
などを書くことで、「直接の会議の方が良いんだ」という、今の時代としては新鮮な(?)提案ができるかもしれません。
「800文字の小論文」作成例-3〈フィットネスジムは必要か〉
長くなりましたが、最後にもう一つやってみます。仕事ではなく、生活寄りのテーマで「フィットネスジムに通うことの是非」という課題でやってみます。
ちなみにフィットネスジムに一時期通ったのは私の経験です(笑)。
フィットネスジムに通うということについて、タイトルを含め800文字以内であなたの考えを書いてください。肯定/否定は問いません。
これも「フィットネスジムに通った方が良い(肯定)」と「通う必要はない(否定)」のどちらの結論でも作れます。どちらでもご自分が思う論調で良いです。(もし課題がどちらかの論調でとあれば、もちろんそれに沿って進めます)
ここでは「通う必要はない(否定)」の方でやってみます。
まず、これまで同様、各パーツを作っていきます。
1「問題提起」
体に気をつけることはもちろんとても良いことですが、本当にフィットネスジムに通うのがベストなのでしょうか。
2「反対意見への理解」
確かにトータルで良い面がいろいろあることは否定しません。
3「自分の意見を提示」
しかし私はそれでもあえて「フィットネスジムに行く必要はない」と考えます。
4「理由説明」
なぜなら、健康作りというものは、なにより「習慣として身に付ける」「長く続ける」ことが大事であり、その観点からすればフィットネスジムは「続けにくい(=健康作りに向かない)」と思うからです。
5「結論」
よって私は、よって私は、フィットネスジムを否定はしませんが、通う必要はないと考えます。
それらベースに書いてみた小論文がこちらです。
健康のためにフィットネスジムに通うべきか? 私が今考えること
近年、健康のためにフィットネスジムに通う人が増えています。
体に気をつけることはもちろんとても良いことですが、本当にジムに通うことがベストなのでしょうか。私は少し疑問を感じています。
私はかつて、3か月ほどですがフィットネスジムに通った経験があります。
そこにはいろんなマシンが置いてあり、体の各部のさまざまな運動ができます。
さらに、運動するしかない環境なのも良いと思います。
有料にはなりますがパーソナルトレーナーの方に指導も受けることができます。確かにトータルで良い面がいろいろあることは否定しません。
しかし私はそれでもあえて「フィットネスジムに行く必要はない」と考えます。
なぜなら、健康作りというものは、なにより「習慣にする」のと「長く続ける」ことが大事であり、その観点からすればジムは「続けにくい(=健康作りに向かない)」と思うからです。
ジムに通うには決して安くない月会費がかかりますし、運動の時間に加えてジムまでの時間も必要になります。
毎月十分な収入や時間のゆとりがある人なら良いのですが、今月はお金が厳しい・忙しい、という時があるとどうしても足が遠のきます(それでも月会費は必要です)。
現在私は毎朝のラジオ体操と、夕方30分のウォーキングを習慣としています。
もちろんこれらも完璧に毎日やっているかというとそうではありませんが、フィットネスに行くことを思うと、ほぼ毎日やっていますし、お金や時間がない時でも、なんら影響されることなく続けることができています。
フィットネスジムのメリットもわかるし良いことだとは感じますが、習慣とすることを中心に考えた時、お金も時間もかからず生活のリズムにもなる、ラジオ体操や夕方30分のウォーキングの方が良いと思ってしまいます。
よって私は、フィットネスジムを否定はしませんが、通う必要はないと考えます。
タイトル含めて798文字です。
自分の意見と言ってもごく当たり前な内容で、あまり良い例でもありませんが、経験を入れつつ800字でこんな感じにまとまる例として書いてみました。
こちらも是非を逆にすることもできます。
「運動はウォーキングなどでも手軽にできるが、お金と時間を遣ってでもフィットネスジムに通う方が良いと、あえて言う」という結論です。
- ウォーキングやラジオ体操は、お金も時間もかからず手軽だが、日々の習慣にすることが難しい
- フィットネスジムという空間に身を置くことで、モチベーションが上がる
- 多彩な器具を使うことで体のいろいろな部位に効果が期待できる
などを書けば、全く逆に「フィットネスジムに通う方が良い」という小論文ができます。書き方にもよりますが、こちらの方がユニークなものになるかもしれませんね。(*^o^*)
「反論容認型/だろうかたしなよ」のテンプレート5ステップを使った小論文作成、いかがだったでしょうか。
どうぞ一つのご参考としてください。
 マッキー
マッキー小論文なんて怖くない! 頑張って合格しましょう!p(^^)q


※一部NHK・Eテレ テストの花道「小論文は“型”で勝つ」を参考にしました
この記事の前段になる「問題提起」についてはこちらの記事をどうぞ


文章作成・添削関連ではこちらの記事もどうぞ↓
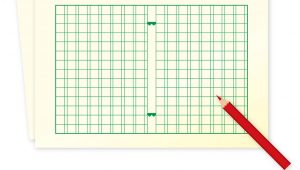
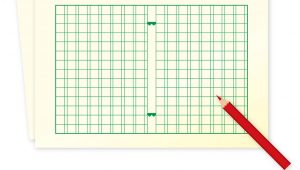



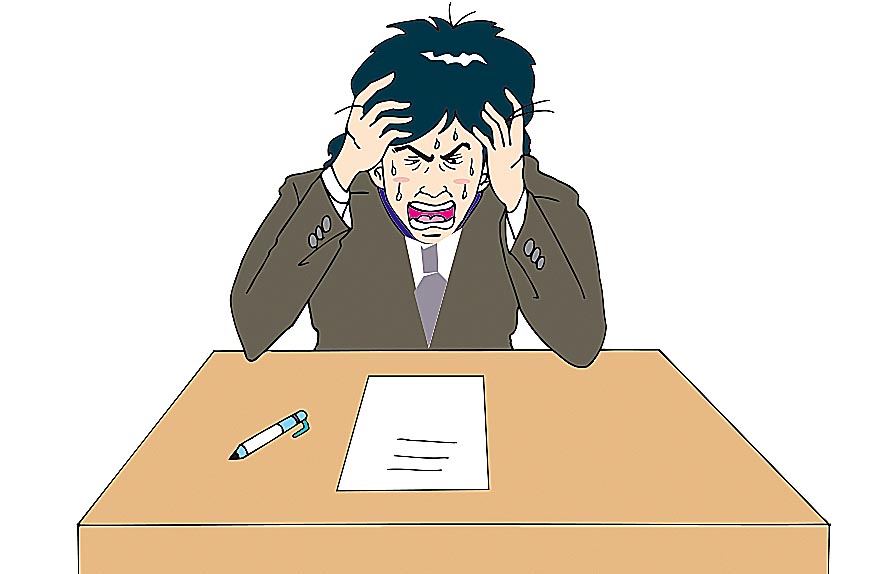

コメント
コメント一覧 (12件)
マッキー様
短大で初の論文課題で、テーマを眺めてはグズグズ、グズグズして何も手につかない最中です。
マッキー様のレクチャーをもとになんとか手を付けてみます・・・論文がトラウマになりそうです(笑)
あっこさん
マッキーです。
ブログへのご訪問&メッセージ、ありがとうございました!
私はもう論文を書かなくてもいい年代になってしまいましたが
まさに今現役で取り組んでいる方は大変ですよね。
グズグズは私も今でもそうですからよくわかります(笑)
どうぞ気軽に構えてまず一歩、進めてみてください。
きっといい論文が書けますように!(*^_^*)
転職で急に小論文有と宣告を受けていましたが。
これを見て俄然やる気が出来てました。
”なんかやれそうな気がする~~” 詩吟です。
ほんとにありがとうございます!
骸さん
管理人のマッキーと申します。
コメントをありがとうございました。
お役に立てて本当に嬉しく思います。(*^_^*)
「なんかやれそうな気がする〜」
はい。その気持ち、大切です。絶対にやれますよ!
どうぞ頑張ってくださいね。心から応援しています。p(^-^)q
マッキー 様
非常にわかり易い内容をありがとうございます。
目からウロコです(;_;)
試験勉強の励みになります(^_^)y
4545さん
マッキーです。おはようございます。
コメントをありがとうございました。
お役に立てたことをとても嬉しく思います。
試験に向けて、大変ですね。
どうぞ体調に気をつけて頑張ってください。
成功をお祈りしています!!p(^-^)q
とても役に立ちました!ありがとうございました。
ぺんたこさん
管理人のマッキーと申します。コメントありがとうございます。
読者さんのお役に立てるのは私にとっていちばんの喜びです。
こちらこそありがとうございました。
これからも頑張ってくださいね! p(^-^)q
来月の公務員での小論文試験に向けて参考になります。自分のやり方と似ていたので、自身になりました。
試験頑張ります!ためになる記事ありがとうございましたm(_ _)m
しゅーかつせーさん
おはようございます。管理人のマッキーと申します。
コメントをいただきありがとうございました。
私の記事がお役に立てたとお聞きし、本当に嬉しく思います。
来月、公務員試験があるんですね。
合格を心からお祈りしています。頑張ってください!
輝かしい未来となりますように!\(^o^)/
ありがどうね。助けてくれたね。
とうはいはい様
管理人のマッキーと申します。
ブログへのご訪問、そしてコメントをありがとうございました。
記事がお役に立てたようで本当に嬉しいです。
そのお言葉が私にとって何よりのモチベーションになります。
今後とも頑張りますので、どうぞよろしくお願い致します。