あなたは成分献血の経験はありますか?
普通の献血(全献血/正式には全血献血と言います)をされた方は多いと思いますが、成分献血をされた方は案外少ないかもしれませんね。
私も全献血はこれまでだいぶしてきましたが、成分献血はずいぶん前に、市内の献血ルームで一度あるだけです。
(成分献血には専用の大きな機械が必要で、通常、献血バスではできないようです。※一部にはできるバスもあるそうですが)
今もいろんなところで「成分献血をお願いします」との日赤からの呼びかけを聞きます。この記事ではそんな成分献血と全献血について、違いやリスクなどをまとめてみました。
私自身、どちらの献血も実体験はありますが、うろ覚えのことが多くて、今回調べてあらためて勉強になったと思います。
もしあなたが成分献血についてよくご存知でなければ、ぜひ興味を持っていただきたいし、ご自身にとって「どちらが良いか」と考えていただくきっかけになれば幸いです。

それではまずそもそも成分献血ってなんだろう?というところからです。(*^▽^*)
成分献血とは
成分献血は、血液中の特定の成分だけを取り出して提供するというものです。
これに対して、普通の献血はそれらの成分ももちろん、血液すべてを提供します。どちらも献血には違いがありませんが、一部か全部かの違いがあります。(成分献血では、機械を通した血液は、再び体内に戻されます)
成分献血には、取り出す成分によって「血小板(けっしょうばん)成分献血」と「血漿(けっしょう)成分献血」というものがあります。私の時は確か血小板献血だったと思います。(赤血球は回復が遅いので取らずに戻すそうです)
ちなみに普通の献血のことを全血献血(全献血)と言います。
成分献血と普通の献血(全血献血)の違いは?
体への負担の違い
普通の献血は400mLまたは200mLの血液を取ってしまうので、健康な人でもやはりそれなりに体への負担があります。時には献血後に体調を悪くする人もあります。
それに比べると成分献血は、血液を抜いてそこから遠心分離機で必要な成分を分離、抽出した上で、また体に戻します。なので全血献血に比べ、循環器への負担が少なく、体に優しいというメリットがあります。
当日の負担も少ないですが、年間の献血可能回数も大きく違います。(あとの項で詳しく書きます)
使用用途の違い
一般に「輸血をする」というと、血液を丸ごと入れるイメージがあります。確かに手術などでそういう必要性も多々ありますが、医学が進んでいくにつれ、血液を全部入れなくても、患者さんに必要なものだけを入れれば良いケースも増えてきました。
それが「血液製剤」と呼ばれるもので、血球成分から作られる「赤血球製剤」「血小板製剤」、血漿成分から作られる「血漿製剤」などが患者さんの状態に合わせて使われます。

成分献血は中でも血小板製剤や血漿製剤を作るために欠かせません。
1人の人から受け取った成分献血から多くの血液製剤を作ることができるそうです。なので全血献血に比べ、大量の人数分を集める必要がないという点があります。
これはイコール、血液中のウィルス感染などのリスクが大幅に下がるということでもあります。
採取にかかる時間の違い
成分献血の最大のデメリットは、時間がかかることです。通常の献血が15分くらいで終わるのに対し、成分献血は1時間くらいかかったりします。(時間は実際に血液を抜く作業の時間で、医師のチェックなど準備の時間は含みません)
ここで一度まとめますね。
| 全血献血 | 成分献血 | |
|---|---|---|
| 献血者の体の負担 | ややある | 少ない |
| 献血時の時間 | 10〜15分程度 | 40分〜1時間程度 |
そういえば私が成分献血した時も、かなり時間がかかったように思います。1時間だったか忘れてしまいましたが、長いと思いました。
でも少し時間がかかっても、体の負担が少ないというのは嬉しいですね。
1年間に献血できる回数の違い
負担が少ないということから、1年間にできる回数も全血献血に比べるとずいぶん違います。
日本赤十字社のホームページからその部分を抜粋させていただきます。
| 成分献血 | 成分献血 | 全血献血 | 全血献血 | |
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 血小板成分献血 | 血漿成分献血 | 400mL | 200mL |
| 1回の採血量 | 600mL以下(循環血液量の12%以内) | 600mL以下(循環血液量の12%以内) | 400mL | 200mL |
| 年齢 | 男性18歳〜69歳、女性18歳〜54歳 | 18歳〜69歳 | 男性17歳〜69歳、女性18歳〜69歳 | 16歳〜69歳 |
| 体重 | 男性45kg以上、女性40kg以上 | 男性45kg以上、女性40kg以上 | 男女とも50kg以上 | 男性45kg以上、女性40kg以上 |
| 年間献血回数 | 血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 | 血小板成分献血1回を2回分に換算して血漿成分献血と合計で24回以内 | 男性3回以内 女性2回以内 | 男性6回以内 女性4回以内 |
| 年間総採血量 | - | - | 400mL献血と200mL献血を合わせて男性1,200mL以内女性 800mL以内 | 400mL献血と200mL献血を合わせて男性1,200mL以内女性 800mL以内 |
引用:日本赤十字社 献血方法別の献血基準より
血小板成分献血・血漿成分献血は相当な回数できるんですね。
- 時間がかかる
- 設置された献血ルームまで行かないとできない
という難しさはありますが、体に負担が少ないのにそんなに人の役に立てるのなら、時々はしたいなと思いました。
これはイコール、血液中のウィルス感染などのリスクが大幅に下がるということでもあります。
成分献血のリスクは?
献血は医療行為です。もちろん十分な管理のもとで安全に行われますが、全くリスクがないわけではありません。
成分献血時のリスクについて主なものを二つ掲載します。
- 献血一般のリスクとして「血管迷走神経反応」という、自律神経のバランス異常があります。これにより血圧低下や脳の血流の低下があり、めまいやふらつき、気分の悪さなどが起こる可能性があります。これは特に献血が初めての方や女性に多く、全血献血より成分献血の方が起こる率が大きいそうです。
- 成分献血では血液が体外に出た時に固まらないように、クエン酸というものを入れますが、まれにそれが唇や指の軽い痺れとなるケースがあるそうです。そういう反応が出た時にはカルシウムを摂ることで改善するとのことです。
これらのリスクについては献血の際に説明があるはずですが、念のため、担当の医師や看護師さんに訊いてみられるといいと思います。
まとめ
成分献血は体への負担が比較的少ないという優れた面があります。
なので多くの方に適しているとは思いますが、上記に挙げましたように、年齢や体重などの制限もあります。決して無理はしない中で、可能であれば成分献血または全血献血の協力をしていただきたいと思います。
確かに献血はリスクがゼロではありません。しかし、自分が多くの方に役立つことができるという喜びは、何物にも代えがたいものがあります。
私もいつしか献血回数がかなり多くなりましたが、引き続き積極的に献血をしていきたいと思います。(*^o^*)
こちらの関連記事もご覧ください。


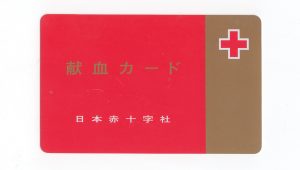


コメント