夏至が過ぎると徐々に本格的な夏がやってきますね。
1年を24で区切った「二十四節気」で言えば「大暑(たいしょ、又はだいしょ)」、そしてその前の「小暑(しょうしょ)」がそれにあたります。
小暑・大暑とはそもそもどういうことを言うのか、どんなことをして過ごすのか、などをまとめてみました。あなたもぜひ日本の昔からの夏の風情を楽しんでください。
ではまず、小暑・大暑とはどういう日(どういうこと)か、という定義的なことからお伝えします。
小暑・大暑の雑学1 小暑・大暑とはどんな日? 3つの定義とは
ちなみに、今年2023年の
小暑は7月7日(金)
大暑は7月22日(土)です。
小暑・大暑には3つの定義(見方による違い)があります。
- 1.「瞬間」としての小暑・大暑
-
天文学的に、小暑は太陽黄経が105度になった瞬間のことを言い、大暑は120度になった瞬間のことを言います。(太陽黄経については次の項でお伝えします)
これは言い換えると、7月7日17時31分が小暑の瞬間、7月22日10時50分が大暑の瞬間ということになります。(参考:国立天文台 暦計算室 令和5年暦要項)
- 2.「日」としての小暑・大暑
-
「小暑・大暑の瞬間を含む日」のことで、これが一般的に「小暑・大暑(の日)」と言われているものです。
- 3.「期間」としての小暑・大暑
-
二十四節気で、小暑の日・大暑の日から約15日間が、小暑(の期間)、大暑(の期間)となります。
二十四節気の図をご覧ください。
太陽黄経って?
先ほど「瞬間」というところで、ちょっと出しましたが「太陽黄径」というものが大きく関係してきます。
ちょっとややこしい話になりますが、図をご覧ください。天球図と呼ばれるもので、地球を中心として太陽がぐるっとまわりを回るイメージを描いたものです。
地球から見て春分点を0度として、太陽の動きを24分割します。その角度を「太陽黄経」と言います。
この場所(この記事の場合、105度の小暑、120度の大暑)を通過する瞬間が、天文学的な意味での小暑・大暑となります。
ちょっと堅い話が続きました。ここから大暑や小暑で何をするのかを見ていきたいと思います。
小暑・大暑の雑学2 小暑・大暑の日には何をする?
小暑・大暑の時期約1か月をカレンダーにしてみましたのでご覧ください。
これに沿っていくつか雑学的なことをお伝えします。
「日」としての、小暑の日・大暑の日に、何か昔からの行事や慣習のようなことはないかと調べてみたのですが、まず、小暑の日には特に行われている習慣や行事のようなものはないようでした。
大暑の日は、昔から打ち水をする風習があります。もしあなたが普段そういうことをしない方でも、この日はぜひやってみてください。涼しくもなり、日本の風情を感じることができますよ。

また、動物園では大暑の日に白くまに氷をあげたりするところも多いようです。動画は大暑の日、大阪・天王寺動物園での、白くまくんへ氷プレゼントのニュース映像です。可愛いです(*^^*)
小暑・大暑の雑学3 (大暑とほぼ重なる)夏の土用の話
さきほどのカレンダーを見ていただくとわかりますが、大暑の時期と夏の土用の時期はほぼ重なります。
この章では、夏の土用の時期についていくつかまとめます。
2023年の土用はいつ?
土用は本来、夏に限らず、春夏秋冬各季節の、最後の約18日間を言います(年により日数がかわることもあります)。
| 土用の入り | 土用の日 | 土用の明け | 日数 | |
|---|---|---|---|---|
| 冬の土用 | 1月17日(火) | 1月19日(木) 丑の日・1月31日(火) 丑の日 | 2月3日(金) | 18日間 |
| 春の土用 | 4月17日(月) | 4月25日(火) 丑の日 | 5月5日(金) | 18日間 |
| 夏の土用 | 7月20日(木) | 7月30日(日) 丑の日 | 8月7日(月) | 17日間 |
| 秋の土用 | 10月21日(土) | 10月22日(日) 丑の日・11月3日(金) 丑の日 | 11月7日(火) | 18日間 |
2023年の夏の土用は「入り」が7月20日(木)、「明け」が8月7日(月)です。
夏の土用の時期、どんな生活をする?
土用の虫干し
夏の土用の期間に、服や布団、本などを陰干しして、カビや害虫から守ろうとするのが「土用の虫干し」あるいは「土用干し」といわれます。
田んぼに水を入れず乾燥させる
雑菌が繁殖するのを防ぎ、稲の根をしっかり張るための工夫です
梅干しの天日干し
この時期特に美味しい梅干し作りが多く行われます。
土を掘り起こしてはいけない
これは昔の「陰陽五行思想」からきているものですが、この時期は「土」の時であり土の神様が支配していて、神様を怒らせないように土をそっとしておくという信仰がありました。今でも土木工事で土を掘り起こす作業を土用のときをはずすこともあるそうです。
(ただし、間日(まび)といって神様がいない時もあって、その時は土を掘ってもいいそうです。面白いですね)
小暑・大暑の雑学4 土用の丑の日の話
夏の土用の中でも、有名なのが【土用の丑の日】ですね。ここでは土用の丑の日にちなんだ雑学をお伝えします。
2023年の「夏の土用の丑の日」はいつ?
2023年の「夏の土用の丑の日」は7月30日(日曜日)の己丑(つちのとうし)です。
なお、干支は12あって土用は約18日間ですから、年によっては2回丑の日が来ることがあります(二の丑といいます)。今年は1回のみです。
土用の丑の日に食べたいもの
四季全てにある土用の中でも、夏の土用だけがよく言われるのは「暑さでバテやすいこの時期、体調を崩さないためのいろいろな工夫が昔からされてきたから」と言われています。
『土用の丑の日』って、美味しいうなぎを食べてパワーをつける日、というイメージですよね(笑)。
うなぎを食べるのも古くから夏の体調維持の一つとして伝わってきました。
他には「土用餅」というお餅を食べるとか、「土用しじみ」を食べるとか。
「う」のつくものを食べる、というのもありますね。「うどん」「梅干し」「うり」などです。
土用の丑の日 その他の風習
江戸時代には丑湯と言って薬草の入ったお風呂に入ったり、お灸をすえる(土用灸)という風習もありました。
暑い夏を乗り切るためにいろんな工夫があったんですね。
小暑・大暑の雑学5 暑中見舞いを出す日の目安と二十四節気
年賀状ほどのやりとりはされませんが、暑中見舞いもいただくと嬉しいものですね。
一般に、夏の土用の間が「暑中」とされ、その間に暑中見舞いを出すものとされています。今年2023年で言えば、7月20日〜8月7日ということになります。(土用のところの図をご覧ください)
なお、小暑から立秋の前日までを「暑中」とする説もあります。その範囲であれば問題ないと思います。立秋を過ぎると「残暑見舞い」として送ります(遅くても8月末まで)。

小暑・大暑の雑学6 手紙の挨拶にも「小暑」「大暑」が使われる
拝啓 何々の候・・などと始まるきちんとした手紙を出すことはかなり少なくなりました。でも、まだまだビジネスその他でそんな手紙文を書かないといけないこともあると思います。
この時期の手紙の書き出しですが・・
7月7日(金)〜7月21日(金)[小暑の時期]は
拝啓 小暑の候
7月22日(土)〜8月7日(月)[大暑の時期]は
拝啓 大暑の候
が自然です。
終わりに
大暑や小暑は、春分の日などに較べ、あまり大きく話題になりませんね。でもあらためてこうしてみると、現代の生活に関わることもいろいろあります。
昔から伝わってきた季節感を大切にしていくのは、毎日に新鮮なものをくれる気がします。
こういうことを知ることで、今の生活をさらに楽しくできそうだなと思いました。
私も今度の大暑には打ち水をしてみようかな・・(*^^*)


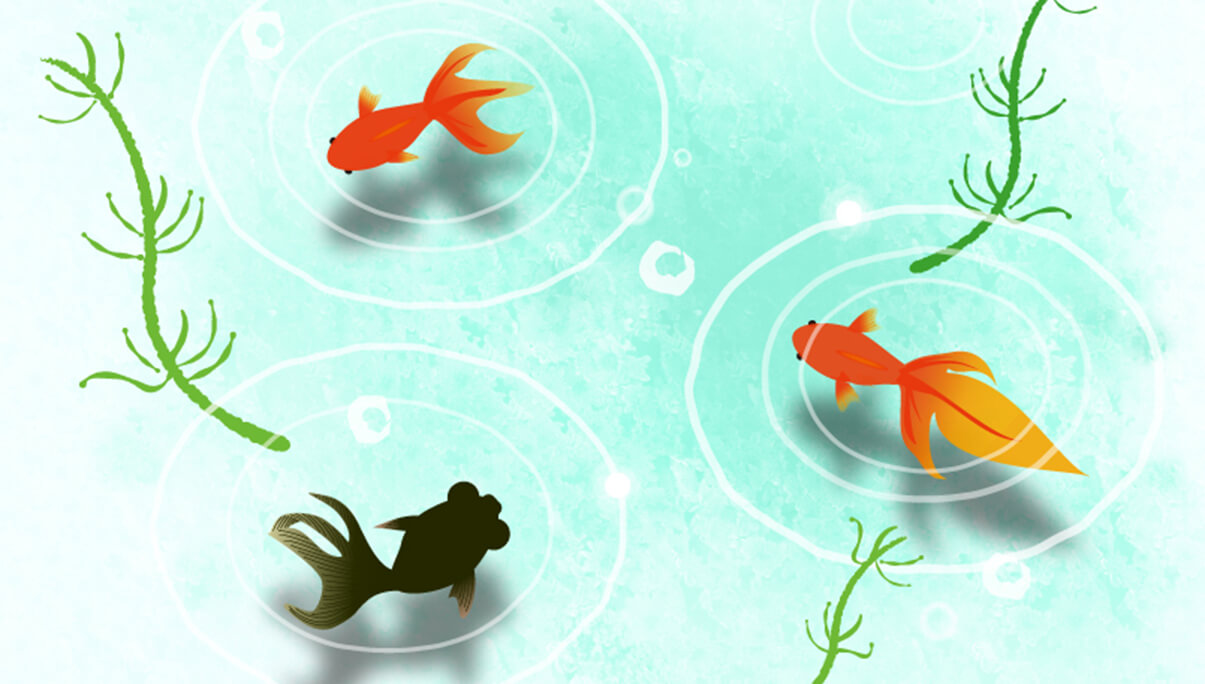





コメント